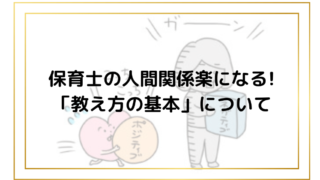PR
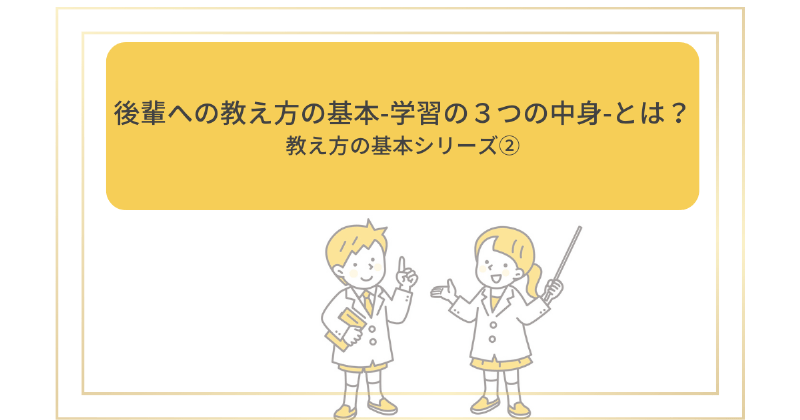
保育士の人間関係がちょっと良くなる!
教え方の基本②-学習とは?
後輩指導、人材育成の立場になった人。もう1度基本から勉強したい人。一緒に学びましょう!
今回は「教え方の基本その②。”学習”の中身3つ」を解説します。

今回は「後輩への教え方シリーズ」第2弾です!

この「教え方シリーズ」は子どもへの伝え方のヒントにもなります。ぜひご覧ください。
「教える」とは「相手が学習する」ことのお手伝い
そもそも「教える」とはどういうことか?
皆さんはイメージがつきますでしょうか。
教えるとは「相手が学習すること」のお手伝いをすることです。
この「学習」という言葉は日頃からよく使われていますが、詳しく中身を分けると3つになります。
①獲得
②参加
③変化

「参加」や「変化」も学習なんですね!
相手の学習をお手伝いにする際、どの中身を相手に学習させるかによって、手法が変わってきます。
まずは自分の指導する相手に対して、どのような中身を学習して欲しいか、取るべきスタンスを決定することが大事です。

それぞれどのような手法で伝えていくのが良いか、は今後解説していきます。
その上で、ゴール設定を行うと、より目標がわかりやすくなります。
それでは、学習の中身をそれぞれ見ていきましょう。
①獲得

「獲得」とはそのままのイメージです。
学習する人が知識・技術・態度などを獲得できれば、学習したということになります。
後輩に指導する時は知識・技術・態度など、足りない部分を教えることで、不足分を補っていきます。

後輩に対してはこの部分の比重が重そうですね

「獲得」の教え方ポイントは今後また詳しく解説します。
②参加

参加に関しては聞きなれない方も多くいらっしゃるかと思います。
参加による学習というのは、新しい環境・コミュニティに所属した時に、自分の力を発揮できるようになること、というような考え方です。
例えば…
5月に新しい保育園から転園してきたAくん。
始めはお仕度の仕方や朝の会の流れ、当番など前の保育園と違う所もあり、うまく参加できませんでした。
しかし、保育士に教えてもらったり、お友達に聞いたりし、少しずつ生活に慣れてきました。
今ではお仕度を完璧にこなし、小さい子に誇らしげに教えてあげています。
保育園や幼稚園ではよくみかけるエピソードだと思います。
ここでAくんは何かを獲得したというわけではありません(もともとお仕度は出来る子なので)。
ですが、Aくんは学習をしていないか、と言われればそうでもありません。
このように、学習とは何かを獲得するだけではなく、持っている力を発揮するまでの過程も学習なのです。

あえて言えば、自信を獲得したのかもしれませんね。
③変化

「変化」とは心理学的観点からみた学習の定義です。
変化とは教わった人が、言葉・表情・仕事ぶりなど、外からみて言動などに変化が見られた場合のことを指します。
「獲得」したから「変化」したんじゃないの?とも思われるかもしれません。
その通りですが、獲得がすぐに学習した、とは言えないケースもあります。
以下の例をご覧ください。
最低でも15分前には必ず職場に到着する先輩Bさん。
先輩Bさんからは「もう少し余裕をもって出勤した方がいいよ。」と指摘されていた。
しかし、Aさんからすれば、「言いたい事はわかるけど、業務開始に間に合えばいいじゃん」と返事はするものの、出勤時間については変えなかった。
しかし、ある日、突然の事故で電車が遅れてしまい、Aさんは15分遅刻してしまった。
遅れて出勤したAさんのクラスをフォローしてくれていたのは、同じ路線をに使っているはずの先輩Bさんだった。
Aさんは過去にBさんに言われた事を思い出し、少し早めに到着するようになった。

子どもも獲得してから、変化するまでに時間がかかる場合がありますよね!

まさに保育は将来の子ども達の変化を期待する職業とも言えます。
まとめ
今回は「教える」ことの基本「学習」について学びました。
・「学習」の中身は3つある。
①獲得
②参加
③変化
・3種類の学習があるのに対して、どこにアプローチをしていくのか?が指導する側が最初に設定すること
・学習の中身を知り、ゴールを設定することで、指導のしやすさがグッと増します!
・「獲得」「参加」「変化」を伝える際のポイントは今後記事にしていきます。

人への教え方シリーズ、今後にこうご期待ください!
すべての子ども関連で働く人へエールを!